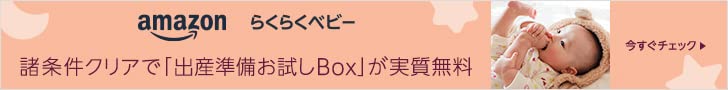子育て本おすすめ15選
イヤイヤ期の困ったときの対応法や言葉かけ、離乳食の作り方など、さまざまなジャンルの子育て本を紹介!
1.「小児科医ママが今伝えたいこと! 子育てはだいたいで大丈夫」(森戸やすみ)

小児科専門医で二児の母でもある著者が、巷でよく取り上げられる育児の疑問について医師の視点で分かりやすく解説する子育て本。
「母乳を飲まないと身体が弱い子になる」というウワサや「9時に寝ないと怒りやすい子に育つ」などの誤った情報ほか、親が不安になるような疑問をテーマ別に紹介。
1冊読めば、情報に振り回されて無駄に心配する…なんてこともなくなる子育て本です。対象年齢は0歳の内容を中心に3歳くらいまでです。
ママ編集者のおすすめポイント!
親世代から「粉ミルクだけで大丈夫なの?」なんて聞かれると、大丈夫と分かっていてもネットで検索をしてしまったりしますよね。
調べ始めるとさらにいろいろな情報が出てきて、結局どれが正しいの?となんてことも。
医師である著者がスパッと言い切ってくれるので、調べたり悩んだりしたりしなくて済みます!
「小児医療の正しい知識」の章では、体調不良になったときの知識が載っていて、目を通しておきたい内容が紹介されていますよ。
2.「マンガで読む 育児のお悩み解決BOOK」(フクチマミ)

自らも育児に悩んだ経験を持つイラストレーターのフクチ マミさんが、あらゆるママの悩みや体験談をもとに専門家に取材をしてできた子育て本。
誰も教えてくれなかった産後の大変な子育ての様子がコミカルにマンガで描かれていて、共感しながら悩みも解決できる一冊です。
対象年齢は0歳ですが、産前に読むのもおすすめですよ。
ママ編集者のおすすめポイント!
「生まれる前に知っておきたかった!」という母親たちの声できた子育て本。
子育ての悩みに対して「私の育て方が悪いから?」「個性だから仕方ない?」「誰に聞いたらいいの?」など、思ったことはありませんか?
私はママ友に相談しても「それぞれだよね~」と締めくくられて、モヤモヤすることもしばしば。
そんな悩みに対し専門家がアドバイスをくれる一冊です。
主人公が子育てに奮闘する姿がリアルに描かれていて、悩んでいるのは自分だけじゃないんだ、とホッとすることも。
とくに育児で疲れていて活字なんて読めない…という状況でも、マンガなので読みやすいところもおすすめですよ。
3.「0~3歳までの実践版 モンテッソーリ教育で才能をぐんぐん伸ばす!」(藤崎達宏)

アマゾンやフェイスブックの創設者をはじめ、日本では藤井聡太棋士が受けていた教育として注目されている「モンテッソーリ教育」。
日本モンテッソーリ教育研究認定講師で4児の父である著者が、子どもの成長にもっとも重要とされる0~3歳のモンテッソーリ流の教育方法を紹介。
基本的な考え方や0歳からお家で簡単に取り入れられる教育法をわかりやすく解説している子育て本です。
ママ編集者のおすすめポイント!
娘が0歳のときに出会い、子育てへの向き合い方がガラリと変わった子育て本。
「子どもがいま何をしたいのか」と、子どもの気持ちを考えることを覚えた一冊です。
たとえばティッシュをたくさん出すイタズラは、引っ張る動きを繰り返しすることでその動きを身につけるのだとか。「だめ!」と言ってしまいそうですが、知っていればイタズラは特訓のように見えて、たくさんさせてあげよう!という気持ちになります。
ちなみにこのような「〇〇がしたい時期」は月齢や年齢で項目が決まっていて、本書では一覧で紹介されています。「今は〇〇がしたいんだな」と子どもの成長がわかるとグッと育児がしやすくなりますよ。
4.「カリスマ・ナニーが教える 赤ちゃんとおかあさんの快眠講座」(ジーナ・フォード)

イギリスのカリスマ・ナニーのジーナさんが、世界中の子ども300人の面倒をみて発案したねんねトレーニングの子育て本。
睡眠・授乳時間をスケジュール通りに行うことで、7時に起きて19時に寝る生活習慣をつけられます。
親がしっかりと睡眠時間を取れるだけでなく、赤ちゃんも夜泣きしない、日中はご機嫌に過ごしていたのになんで泣いているのかわからない、ということで悩まない魔法のようなメソッドが紹介されています。
0歳児向けの子育て本です。
ママ編集者のおすすめポイント!
「子どもが産まれても、絶対に寝たい…!」と思い、妊娠前から読み始めた子育て本。
産後の体力&精神的に大変なときに、スケジュール通りに進めることは根気がいりますが、しばらく経つと時間になったらベッドに置くだけで寝てくれるようになります。
ジーナ式を知っている友人からは「赤ちゃんが泣いても抱っこしちゃいけないんでしょ?耐えられない」と言われることもありましたが、そこまで厳しくしなくてもスケジュールを守るように心がければ、習慣はついていきますよ。
お腹が空く・眠たくてぐずる前に、睡眠やお昼寝の時間がくるように設定されているので、赤ちゃんにも負担がないようで常にご機嫌でした。
私の0歳の子育てはジーナ式なしでは成り立たなかったといっても過言ではありません!
ただ本の構成がわかりづらいうえ、翻訳されたものなので表現も難しいのは少し難点です。
じっくり読みたい方にはぜひおすすめしたい子育て本です!
5.「世界トップ機関の研究と成功率97%の実績からついに見つかった! 頭のいい子にする最高の育て方」(はせがわ わか)

出産をきっかけに子育て本マニアになった著者が、世界中の育児に関する研究結果をもとに、実際に効果のあったものだけを体系化した一冊。
インパクトがあるタイトルですが、読みやすい子育て本です。
また、本書の特徴は「親のタイプは子どもに遺伝する」という考え方。3分でできる親のタイプ診断がついていて、子どものやる気はどのようにしたら出せるのかも紹介されています。
対象年齢の明記はありませんが1~5歳がメインです。
ママ編集者のおすすめポイント!
内容は決して「ガリ勉」の育て方ではありません!
子どもへの愛情のそそぎ方やご褒美の仕方など親ができる働きかけが中心に紹介されています。さまざまな研究がエビデンスとして分かりやすく紹介されていて、「そうなのか!」と驚きがたくさん。
知育に興味がある親のみならず、すべての親に共通する内容も書かれています。
幼児関係で有名な研究が多く紹介され情報がまとめられていているので、色々な本を読まずともこの一冊で読み応えがありますよ。
子育て本を読み漁っている私としては、貴重な知識を体系化してくれるなんて…!と感激してしまいます。
父親の大事な役割についても書かれているので、父親にもおすすめできる子育て本です。
6.「はじめてママ&パパの離乳食」(上田玲子)

定番人気の離乳食本。はじめて離乳食を作る親向けに離乳食の始め方や注意事項などを約200ページにわたって詳しく紹介。
掲載されている300ものレシピは、時期別の献立レシピのほか、食材ごとのレシピも充実しています。
本のサイズは大きめでオールカラー。料理しながら見やすいのもポイントです。
内容は2歳くらいまでの幼児食までをカバーしています。
ママ編集者のおすすめポイント!
私は料理が苦手なのでいろいろな離乳食本を試しましたが、結局この本に戻ってくる、という頼れる存在の本でした。
その理由は何と言っても、一日の必要な食材の量が実寸大の写真で載っているところ!
グラムで書いてある本が多いのですが、食材ごとに計るのが面倒なのでほんとうに助かりました。
あと離乳食本は小さいお皿に料理が盛られていて、写真で見ると量が多そうに見えるのですが、その錯覚もこの本で解消できます。
離乳食の教科書のような本なので、こちらの本を基本に、子どもの味の好みや作りやすさに合わせてほかのレシピ本を併用していましたよ。
7.「子どもの脳と心がぐんぐん育つ 絵本の読み方 選び方」(仲宗根敦子、篠浦伸禎)

1日10分でできる、IQ・EQをのばす「絵本の読み方」・「選び方」がテーマの子育て本。
日本を代表する脳神経外科医である篠浦伸禎先生監修のもと、絵本を活用した子育て経験のある著者が紹介しています。
そのメソッドはゆっくり読まない・声色を変えない・読んだ後に子どもをほめる、というもの。
読み聞かせの効果や選ぶときのポイントが明記してあるほか、年齢別のおすすめの絵本120選の掲載も。
ママ編集者のおすすめポイント!
絵本を日々読んでいて、「子どもにとって良い絵本の読み方ってあるのかな」と思い出会った本。
育児中に夫を失った著者が、1日10分絵本を読み聞かせを続けたことをきっかけに生まれた子育て本です。
絵本にある美しい言葉やワクワクするストーリーには肯定的な世界が広がり、子どもも親も前向きになれる、そして絵本を通して子どもの好きなものや興味が見えてくる、そんな気づきがあると著者は伝えています。
メソッドとしては今までの読み聞かせと真逆のものであるにも関わらず、脳科学的に良いというエビデンスがしっかりあり説得力のある子育て本ですよ。
8.「子どもに伝わるスゴ技大全 カリスマ保育士てぃ先生の子育てで困ったら、これやってみ!」(てぃ先生)

13年目の現役男性保育士であるてぃ先生による子育て本。
保育士の視点と独自のアイデアで子育ての「困った!」を解決してくれると、ツイッター・ユーチューブともにフォロワー50万を超える人気ぶり。
こちらの子育て本では「おしたく」「お片付け」「ごはん」など状況別に、「こんなときはこうするといい!」というテクニックを紹介しています。
ママ編集者のおすすめポイント!
「なるほど!」と、親では考えつかない斬新なアイデアがたくさん!
たとえばご飯をなかなか食べてくれない子どもには食事を「チケット制」にする、などといったもの。
ついつい「食べて!」と言ってしまいそうなことでも、子どもが自ら動くアイディアを教えてくれます。
また項目別で紹介していて目次から気になるページに飛べるので、1冊読まなくても完結できるのも使いやすい!
親からするとちょっと準備に手間がかかりそうですが「やって」「やらない」のプチ喧嘩をせずに、子どもがノリノリで動いてくれるなら試してみる価値アリです。
9.『「私、子育て向いてないかも」がラクになる本』(Joe)

より賢い子を育てる育児本が多いなか、「どうしたら子どもが育つのかもわからない」と不安な親もたくさんいます。
モラハラ対策カウンセラーである筆者が、そんな子育てに自信のない親に向けて書いた、「とりあえずこれだけはやっていれば大丈夫!」という育児を教えてくれる本。
4~12歳の子どもがいる、子育てに追い詰められた人・新ママ&ワンオペの人・自身がしっかりと幼児教育を受けてこなかった人などを対象にした子育て本です。
ママ編集者のおすすめポイント!
2021年12月発行の画期的な子育て本!
私の子どもは対象年齢より低いのですが、精神的に追い込まれたときこのメソッドを活用していて、安定した気持ちでその日をやり過ごすことができます。
子どもを尊重した育児方法が主流となる中で、子どもに対しては最低限のルール意外は何も考えずに、この本通りの振る舞いをすれば良い、というもの。
その振る舞いは子どもにとってもプラスになるメソッドで、母親も不思議と気分が明るくなるのです。
肩の荷が降りて、前向きに楽しく子育てができる気がしてくる一冊ですよ。
10.『モンテッソーリ教育が教えてくれた「信じる」子育て』(あきえ)

モンテッソーリ教師の資格を持つ著者が教える、子育ての困ったシーンで活用できる対応法をまとめた一冊。
0〜6才のとくにイヤイヤ期以降に起こる「駄々をこねる」「遊んだものを片付けない」など、親の悩みの種を子どもの心の状態とともにモンテッソーリ教育式の子どもへの関わり方を紹介してくれます。
タイトルにある「信じる」とは、子どもだからできないと思わずに、子どもを信じてサポートしていく姿勢で子育てをしてほしいという著者の思いからきています。
ママ編集者のおすすめポイント!
ユーチューブで著者・あきえさんの存在を知り、子育て本が出たということで購入をしました。
子どもが一人の人間としてリスペクトされてほしい、という著者の子どもへの愛が感じられる本です。
一貫して丁寧に伝え、子どもが挑戦し、親が環境を整えてサポートしてあげることを大切にした内容。
親の根気が要りそうに見えますが、モンテッソーリ教育のこのメソッドは我が子の0~1歳の子育てにとても有効でした。
歩けるようになったころにはおもちゃを自ら元の場所に片付けたり、まだ言葉をしゃべれずとも事前に伝えれば癇癪したりすることなく動いてくれることが多いです。
11.「自分でできる子に育つ ほめ方 叱り方」(島村華子)

モンテッソーリ教育とレッジョ・エミリア教育を知りつくしたオックスフォード児童発達学士による、3~12歳向けの言葉かけをテーマにした子育て本です。
「えらい!」「すごい!」「だめ!」が口ぐせになっている人や、自分の褒め方や叱り方は大丈夫?と気になる人は必見。
とても読みやすくイラストでの説明もあるので、さくっと読んで実践しやすい子育て本ですよ。
ママ編集者のおすすめポイント!
ついついなんでも「すごい!」と褒めがちな私にとって、褒めると逆効果になることもある、という驚きがあった子育て本。
さらに誤った𠮟り方をすると、子どもがどのような回避行動や考え方をするのかも紹介されていて、親の日々の言葉かけが悪いように影響してしまうことにゾっとしました。
褒め方・叱り方のポイントが分かりやすく紹介されていて、その日から試せそうなところも魅力。
叱り方については、毎日気づくと「だめ」を連呼している私にとっては、とっさに出てくるひと言を文章にするのは至難の業で、本書の理屈は分かっていても難しそう…という気もしています。
頭の片隅に置いて余裕のあるときに実践するのが良さそうと感じました!
12.「お母さんの自己肯定感を高める本」(松村亜里)

子育てシーンでキーワードとなる「自己肯定感」。
自己肯定感の高い子に育ってほしいと願いつつ、親がネガティブになっているなんてことも。
心理学をベースにした書き込みできる14のワークがあり、自分を深堀しながら元気になれる一冊。
育児に追われて自分のことを後回しにしている人や自分に自信を失っている人におすすめですよ。
ママ編集者のおすすめポイント!
育児を頑張るお母さんに向けた子育て本。
育児に専念しているとあらゆる理由から自己嫌悪になってしまうことってありますよね。
母親が元気で幸せな状態でいることが、子どもの幸せにも繋がることを気付かせてくれる一冊です。
本を読んで解決、ではなく、ワークをして自分を見つめなおす時間が持てるのもこの本ならでは。
また著者は母子家庭で育ち、中卒で大検を取り、ニューヨーク私立大学を首席で卒業した異例の経歴の持ち主。
前作『世界に通用する子どもの育て方』からファンも多い一冊です。
13.「言うこと聞かない!落ち着きない!男の子のしつけに悩んだら読む本」(原坂一郎)

母親にとって理解不能な存在の男の子。
じっとしていられない・注意したそばから同じいたずらをする・したいと思ったら止まらない…。
そんな男の子ならではの子育ての悩みを、23年間の保育士の経験を持ち、私生活でも2男1女の父親である著者が解決してくれる子育て本です。
男の子の特徴やしつけの仕方、知っておくと楽になる考え方を紹介しています。
1~5歳向けの子育て本です。
ママ編集者のおすすめポイント!
多くの育児本では、そんな上手くうまくいかないよと思ってしまう内容も多いなか、長年保育の現場で働いていたからこそ、男の子の育児がいかに大変かの理解があり、日常の困るポイントをしっかり押さえた子育て本。
そのため本書を読みながら「息子の特徴、まさにこんな感じ!」と共感する母親も多い一冊です。
男の子の興味や好奇心などを代弁したような本で、「男の子の性質を理解して、いろいろ納得できた」「イライラが減った」という口コミも。
とくに、のびのびと育ってほしいけど、最低限マナーは守れるようになってほしいと願う親におすすめですよ!
14.『子どもも自分もラクになる 「どならない練習」』(伊藤徳馬)

スポーツや音楽、勉強の練習はするのに、子育ての練習をする場はほとんどない—。
その疑問に着目した著者が、本書を通して時代に合った「伝え方」や「褒め方」などを気軽に楽しく教えてくれる子育て本。
コミュニケーションがとれる4歳~小学校低学年向けです。
「こんなときどうしますか?」というお題に対して、どのような声掛けが良いかクイズに応えて練習していきます。
ほかの子育て本と異なり、自分で答えを考えるので能動的でより実践的な内容になっています。
ママ編集者のおすすめポイント!
怒らない「練習」が必要、という新しい視点を持たせてくれた子育て本。
怒ってしまっても「自分はまだまだ育児の練習中だから仕方ない」と諦めがついて、怒ったあとの罪悪感にさいなまれることなく、切り替えができるようになったきっかけの本です。
クイズは「ちゃんとして!」などの言葉を、肯定文にしてみると?といった内容で、意外とすぐに出てこない内容ばかり。
例題を解いていくクイズ感覚でできて、自分が否定的な言葉を使い、子どもに分かりづらい伝え方をしていることに気づかされます。
伝え方のテクニックやレパートリーを増やしていくことが怒鳴らない練習なのだなぁと感じています。
15.「1歳半~5歳 はじめてママとパパでも 子どもと食べたいレンチン作りおき 」(中村美穂)

レンジでチンするだけで簡単に作り置きメニューが作れるレシピ本。
1歳半~5歳向けのレシピを紹介しています。
30分以内で3品できる14日分のレシピのほか、余ってしまいがちなおかずをアレンジして作るメイン料理などアイデアがたくさん。
離乳食が終わって献立に悩んでいる人や子どもが食べてくれなくてご飯作りがつらい人、料理の時間を減らしたい人におすすめです!
ママ編集者のおすすめポイント!
30分以内で3品、しかも火を使わなくて良い、というのに惹かれて購入したレシピ本。
ネットで調べればたくさんレシピは出てくるのですが、検索するのすら面倒なときってありませんか?
とくに私は料理が苦手で元々レパートリーも少なく、頑張って作っても食べてくれないと気持ちが落ち込みます…。
しっかり料理を作る気力や時間がないときは、こちらの本の出番。
栄養もしっかりとれる1食3品がレンジでさくっと作れて、味付けのマンネリ化も防げますよ。
保存期間が冷蔵3日のほか、冷凍14日のレシピもあるので、少量でも余ったら冷凍して、料理が作れない!というときに冷凍した料理を寄せ集めるだけで十分ワンプレートごはんになります。
火を使わないので、料理初心者さんやパパにも挑戦しやすくおすすめですよ!
知育系の子育て本おすすめ3選
「将来、子どもが困らない教育をしてあげたい」。
子どもの教育環境は親がコントロールできるからこそ、どうしたらより良い育児ができるか考えてしまうものです。
今回は生まれたばりの0歳の赤ちゃんの教育、人生でもっとも大切だといわれる3歳までの教育、18歳までの世界標準の子育てをテーマにした3冊をセレクト。
教育ママになるつもりはない…と思っている人も、内容が難しくないので意外と読んでいて「なるほど、なるほど」と興味をもてるはず。
なによりも子どもへの理解が深まりますよ。
16.「Newsweek 0歳からの教育 知育編」(メディアハウスムック)

Newsweek日本版より発行されている、0歳の知力や心の発達を科学的に読み解いていく子育て本。
成長のメカニズムや一般的に知られていない知力の程度が世界の最新の論文を元に紹介されています。
たとえば赤ちゃんのときから英語を聞かせていればバイリンガルになるか、テレビや電子機器の関り方など、よく話題にされる議題についてエビデンスを元に話が展開されていきます。
ママ編集者のおすすめポイント!
少し言葉の言い回しが難しいものの、さまざまな研究結果が一冊にまとめられていて驚きが多い子育て本。
Newsweekでは「0歳からの教育」がシリーズ化されていて、2022年の最新版もあります。
知育がテーマの2017年版は、0歳の赤ちゃんの発達を細かく紹介。
言葉でのコミュニケーションが取れない赤ちゃんが、いまどのような成長段階なのか理解するのを手助けしてくれます。
ゲームで頭がよくなるという話もあって、興味深かったです。
17.「3歳までに絶対やるべき幼児教育」(佐藤亮子)

3男1女全員を東大の理科Ⅲ類に入学させた「佐藤ママ」。その育児法が注目を集め、2019年に書籍化されました。
絵本や童謡を3歳までに一万回読み聞かせる、2歳までに公文式に通わせる、小学校入学前から九九を覚えさせる…など著者流の教育メソッドが詰め込まれています。
スマホは子どもの前で触らない、など真似するには難しいものもありますが、一体どんな子育て法なのかぜひ読んでみてください。
ママ編集者のおすすめポイント!
本を読んでみて、著者の子どもへの愛情を強く感じたのが第一印象。
「こんなときはどうしたら良い?」といつも考えていて、問題解決のために調べた結果こう決断した、など過程も書かれているので、単なるメソッド本よりも母親としての考え方や振る舞いをリアルに感じ、もはや尊敬する気持ちも。
内容は絵本や童謡、あやとり、折り紙など昔ながらの遊びをベースに、「基礎」を大切にするというもの。
おすすめの本や教材なども詳しく紹介されていて、私はさっそく影響されていくつか試してしまいました…!
18.「世界標準の子育て」(船津徹)

20年以上、日本と海外の教育現場を見てきた著者が、世界各国で行われている子育ての方法や実情、日本との違いを体系化。
グローバル化が進む社会で、乗り越えていけるタフな心や地頭の良さを培うためのメソッドを日本人向けにアレンジ。
その根幹となる「自信」「考える力」「コミュニケーション力」を育む実践方法を0~6歳・7~12歳・13~18歳のステージ別に紹介しています。
ママ編集者のおすすめのポイント!
将来子どもにグローバルな人になってほしい、と思う親は多いのではないでしょうか。
我が家では外国語教育は取り入れていませんが、私も少なからずその一人です。
本書を読むと、日本の教育は時代が変わっているのにもかかわらず、学校の制度や教育される価値観がそのままであることに気づかされます。
日本で普通に生活しているとなかなか知る機会のない世界の教育がどのようなものかを少しだけ知り、変化する時代のなかで親が家庭でできる子育ては何かを考えるきっかけになりますよ。
※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

【筆者】ブラックフィッシュ
SNS
国内、海外を問わず、旅行系のメディアを制作するチーム。30年近くにわたって、旅行ガイドブックや旅雑誌などを制作し続けています。とくに箱根や千葉、新潟は、現地での広いネットワークを生かして多彩な情報を発信。各地をじっくりとめぐったからこそ見つけられた、知られざる穴場スポットも続々と発掘していきます。 さらに、それぞれ異なる趣味趣向を持ったメンバーが集まっていますので、多彩なジャンルの記事も手がけていく予定です!