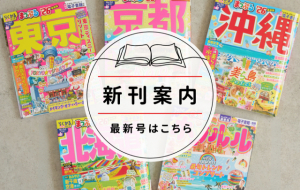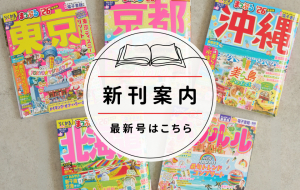更新日: 2024年7月26日
最近話題のモルックってどんなスポーツ?道具やルールを解説
「モルック」って知ってますか?
最近テレビでも見かけるようになったモルックは、フィンランド発祥のスポーツ。
スポーツといっても、モルックと呼ばれる木製の棒を投げて、スキットルと呼ばれるピンを倒し点数を競うというシンプルなスポーツなので、大人も子どもも一緒にモルックを楽しめます。
キャンプでも楽しめるほか、公園など屋外で気軽にプレイできることから、モルックはじわじわと人気になっているんです。
今回は、日本モルック協会(JMA)公認団体の「コレステローラーズ」の皆さんにご協力いただき、モルックとは一体どんなスポーツなのか、モルックの遊び方や道具、ルールについてご紹介していきます。
最近話題のモルックとは?

モルック(木の棒)を投げてスキットル(ピン)に命中させる
最近名前を聞く機会が増えた「モルック」は、フィンランドの伝統的なゲームを元に開発されたスポーツ。
コレステローラーズ代表の釜谷さんによると、フィンランドでは、サウナと食事やビールを楽しみながら、気軽にモルックをプレイするのが主流なのだとか。
休日に家族や友だちと、ピクニック気分で楽しめるのが、モルックの魅力なんですね。
モルックは、「モルック」という木の棒を投げて、「スキットル」と呼ばれる12本のピンを倒し、点数を競うゲーム。通常2チームで対戦して、先に50点ちょうどを取ったチームが勝ちになります。
公式のモルックの大会では決められた人数で行いますが、家族や友だちと遊ぶなら、チームの最少人数はひとりでもOK。何人でもプレイできますよ。

公園で気軽に仲間と楽しめる
モルックは、公園やグラウンド、キャンプ場などの土の上や芝生の上で、幅3〜4m、長さ6〜7mほどのスペースがあればプレイ可能。激しい動作はないので老若男女、誰でも楽しめるスポーツです。
モルックに必要な道具って?
ここからはモルックで使う道具をご紹介します。どんな道具が必要なのか、ひとつずつ見ていきましょう。
モルックに必要な道具1.モルック

スポーツの名前にもなっている「モルック」とは、こちらの木の棒のこと。
長さ20cmほどで、このモルックを投げてスキットルというピンを倒します。
慣れてくると、モルックの持ち方を変えることで、狙ったスキットルを倒せるようになるそうですよ。
モルックに必要な道具2.スキットル

モルックを投げて倒すピンが「スキットル」。全部で12本あり、1から12の番号が書かれています。
倒れたスキットルに表示された点数や本数が得点になります。
モルックに必要な道具3.モルッカ―リ

地面に置いてモルックを投げる位置を示す道具が「モルッカ―リ」。
モルッカ―リからはみ出さないように気を付けて、モルックを投げます。
モルッカ―リは木の枝などで代用することもできるので、最初はなくても大丈夫ですが、モルックとスキットルは必ず必要な道具です。
モルックとスキットルはセットで販売されていて、通販でも購入することができます。
モルックにあったら便利な道具1.得点板

モルックとスキットルがあればゲームはできますが、友だちや家族とモルックを楽しむなら、得点板もあると便利。
チームの現在の得点がわかりやすいうえ、一気に試合らしくなって、盛り上がりますよ。
モルックにあったら便利な道具2.得点記録用のノート

モルックの道具のセットに得点記録ノートがついているものもあります。
記録をしておくと誰が何点取ったのかを後で見直すことができて、次の試合の参考にもなります。
モルックにあったら便利な道具3.メジャー
モルックを投げる位置(モルッカ―リを置く位置)と、スキットルを並べる位置との距離は、3~4mと決まっています。
仲間同士でモルックを楽しむなら、歩幅でだいたいの距離を測ってもいいですが、距離を測るメジャーがあると便利。事前に必要な長さにカットしたひもを持参してもいいですね。
モルックの基本的なルールを知ろう
次にスキットルの並べ方やモルックの投げ方、点数の数え方についてご説明します。
スキットルの並べ方とモルッカ―リの置き方

投げる位置からスキットルまでは3~4m
モルックを投げる位置にモルッカーリを置いて、3~4m離れたところにスキットルを並べます。公式の試合では通常3.5mと決まっているそうです。
モルックを投げる際にモルッカーリに触れてしまったり、モルッカ―リからはみ出してしまったりするとファウルとなり、0点で次のチームに交代になります。

スキットルの並べ方は覚えるまでちょっと難しい
スキットルは写真のように、並べる順番が決まっています。
左側に奇数、右側に偶数、9は一番奥の真ん中に、10以上の数字は中央に並べるのですが、ちょっと難しいですよね。
覚えるまではスマホで写真を撮るなどして、確認しながらスキットルを並べましょう。
モルックの基本的なゲームの流れ
スキットルを並べたらゲーム開始!モルックの基本的な進め方をご説明します。
1.通常2チームで対戦するのでまずはチーム分け。続けて先攻後攻を決めます。

モルックはグループでも1対1でも楽しめる
2.先攻チームが、モルックを投げてスキットルを倒します。

モルッカ―リからはみ出すとファウルになるので注意
3.得点ルールに従って、倒れたスキットルの得点を数えます。得点の数え方はこの後ご説明します。

得点をノートに記録しておくと数え間違いがない
4.倒れたスキットルを倒れた位置で立て直し、続けて後攻のチームがモルックを投げます。

倒れた位置から動かさないように立て直す
モルックは、先攻と後攻のチームが1投ずつ交互にモルックを投げ、先に50点ピッタリになったチームの勝ち。
スキットルは倒れた場所に再び立て直すので、モルックを投げるたびに、どんどんスキットルがバラけていきます。試合が進むと、どのスキットルを狙えばいいのか、戦略が必要になるそうですよ。
モルックの持ち方と投げ方

モルックは下手投げで投げるのが基本
モルックは下手投げで投げるのがルール。
モルックを地面にバウンドさせたり、転がしてスキットルに当てたりしてもOKです。
持ち方に決まりはありませんが、縦に持ったり逆手に持ったりと、スキットルの並んでいる状態によって、狙いやすいモルックの持ち方を工夫して投げているのだとか。
試合開始1投目は、1カ所にまとまったスキットルを倒すため、ある程度強い力でスキットルに当てる必要があります。モルックを水平に持って、力を込めて投げるとうまく倒れるそうです。
スキットルが散らばった状態で、ピンポイントに倒したいスキットルがある場合には、モルックを縦に持ち、倒したいスキットルだけを狙うように投げるのがコツです。

スキットルにうまく当てるには、モルックをリリースするタイミングが重要
モルックを投げる際、モルッカーリの内側に立った状態で、万一モルックを落としてしまうと、1投とカウントされ、次のチームに交代になってしまうので注意しましょう。
また、チームのメンバーが3回続けてスキットルを1本も倒せなかった場合は、そのチームは失格負けになるのでご注意を。
モルックの 得点の数え方
モルックで特徴的なのが得点の数え方です。ちょっと複雑なので、ケースごとにご説明しましょう。
<スキットルが1本だけ倒れた場合>

写真のように、スキットルが1本だけ倒れた場合は、倒れたスキットルに書かれている数字が得点になります。上の写真の場合は3点が得点です。
<スキットルが2本以上倒れた場合>

スキットルが2本以上倒れた場合は、倒れた本数が得点になります。
上の写真の場合は、スキットルが8本倒れているので8点です。
<スキットルが完全に倒れていない場合>

スキットル同士が重なるなど、完全に倒れていないスキットルは、得点になりません。
上の写真の場合、下の11のスキットルは倒れているので得点になりますが、10のスキットルはカウントされません。
モルックはどうやったら勝敗がつくの?

もう少しで50点のチームは狙ったスキットルを倒せるかが大事
モルックの最大の醍醐味といえるのが、ピッタリ50点になったチームが勝ちということ。
この「ピッタリ」というところが難しいんです!
得点を重ねて50点を超えてしまった場合は、なんと半分の25点に減点され、そこからゲームが続行します。
なので、50点が近くなると、どのスキットルを倒せばいいのか、相手チームを50点にさせないために、どうやって邪魔をするかなど、戦略をめぐらせることになります。
ゲームに時間制限はないので、ピッタリ50点になるまで、攻防が続きますよ。
単にスキットルをたくさん倒せばいいだけではない、この頭脳プレイがモルックの魅力なんですね。
通常モルックの試合は、先攻後攻を入れ替えて2ゲーム行い、合計得点が多いチームが勝ちになります。2ゲームとも同じチームが先に50点になれば、もちろんそのチームの勝利です。
誰でも気軽に楽しめるモルックに挑戦してみよう!

「モルックの良いところは、年齢問わず誰でも参加できるところです。スポーツといっても筋トレが必要なわけでもありませんし、本場フィンランド流に、お酒を飲みながらゆる~く楽しめるのもいいですね。それと、モルックの日本代表になるのは非常にハードルが低く、日本モルック協会の登録を受ければ、誰でも日本代表として世界大会に出場することができるのも魅力です」とコレステローラーズ代表の釜谷さん。
実際、コレステローラーズの皆さんは、2022年のモルック世界大会に出場予定なんだそうです。
取材中も楽しい雰囲気でゲームが進み、もう少しで50点というところでは、ピッタリの点数分のスキットルを倒せるか、メンバーの一投に注目が集まり盛り上がります。
体力にかかわらず、ゲーム感覚で気軽に楽しめるモルック。家族や友だち同士で、ちょっと体を動かしたいときにもおすすめです。
テレワークが続いたときや、気分転換や運動不足の解消に、ぜひモルックに挑戦してみてはいかがですか。
モルックの道具をチェック
国内の新着記事
※掲載の情報は取材時点のものです。お出かけの際は事前に最新の情報をご確認ください。

まっぷるトラベルガイド編集部は、旅やおでかけが大好きな人間が集まっています。
皆様に旅やおでかけの楽しさ、その土地ならではの魅力をお伝えすることを目標に、スタッフ自らの体験や、旅のプロ・専門家への取材をもとにしたおすすめスポットや旅行プラン、旅行の予備知識など信頼できる情報を発信してまいります!